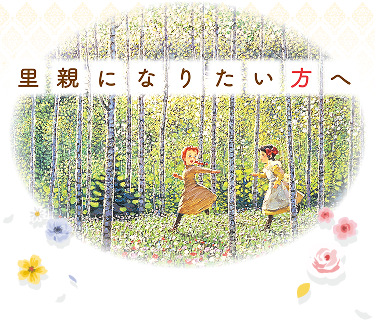里親家庭に迎え入れられたこどもは、どんな思いを抱いて家庭での日々を過ごしているのでしょうか。困難な環境を経てきている子も少なくなく、さまざまな感情が交錯しているかもしれません。こどもの気持ちについては、里親希望の人、検討中の人にとっても、気になるところでしょう。社会的養護の改革をめざすNPO法人「IFCA(イフカ)※」で当事者として活動する20代の里親家庭経験者3人に、お話を聞きました。浮かび上がってきたのは、三者三様の思いでした。
※IFCA:インターナショナル・フォスターケア・アライアンス
自分の意見を言えるように。初めてできた「口答え」
―山本愛夢(あむ)さん(26)

私が里親さんの家に迎え入れられたのは、15歳のときです。それまではシングルマザーの母親とふたり暮らしでした。
母はとても真面目な人で、私は「世間から母子家庭だからと後ろ指を指されないように」と、とても厳しくしつけを受けました。それが行きすぎて暴言や、暴力になることもありました。
覚えているのは小学1年生のとき、私が学校に行きたくないと駄々をこねて母の鏡台の下に隠れたとき、母が私の首をつかんで引きずり出したことです。母からしたら「首をつかんだ」なのかもしれませんが、私は首を絞められて苦しかった。高校生のとき、「あんたのせいでストレスで耳が聞こえなくなった」と母に言われました。母を病気にしてしまうくらいなら死にたいという思いを担任に伝えたところ、そのまま一時保護所に保護されました。
当時は一時保護所から学校に通うことができなかったので、急いで受け入れ先を探してもらいました。そこで受け入れてくれたのが、2年間生活することになるご家庭でした。初めておうちに行ったときの印象は「ネコがいる!」です(笑)。母と暮らしていた家ではペットを飼っていなかったので、3匹もネコがいる状況に驚いたのを覚えています。
そのご家庭はお子さんがいなくて、里母と里父のご夫婦で暮らしていました。「もう15歳だし、私たちのことは好きに呼んでくれていいよ」と言って、束縛せず、自由にさせてくれました。でも、それが私にとっては不安の種で……。生みの母は私のすべてを把握して管理する人でした。どこに行くのか、誰と会ってどんな話をしたのか、すべて聞かれるような生活だったので、放任してくれる里親に対し「私のこと興味ないのかな」と、心配になってしまったのです。でも、里親と生みの母の話をしていて、ふと、「自分にとっては生みの母が人生のすべてになってしまっていたな」と、客観視できるようになりました。自分は生みの母との生活しか知らなかったので、母親に行動を管理されるのが当たり前だと思っていたのです。

里親をサポートする仕組みを充実させてほしい
里親家庭で生活するようになって一番変わったのは、自分の意見を言えるようになったことです。それまでは、親に口答えするなんて絶対に無理だし、考えたこともなかった。でも、里母に対して反抗したり、自分の意見を言ったりすることができるようになりました。それは、里親が私を対等に見て、話をちゃんと聞いてくれたからだと思います。里母は優しい人でしたが、結構、私の反抗に言い返すタイプだったんですよ(笑)。
大人になったいま思い返すと、こどもがいなかった里親にとって私は初めてのこどもで、どうしていいのかわからないことも多かったのではないでしょうか。里父はちょっと高圧的なところがあったし、里母も、私が嫌みだなと感じるようなことをつい言ってしまうこともありました。でも、里親だって一人の人間ですから、そういう部分があるのは当然です。大切なのは、里親が「独りじゃない」と感じられること。里親の悩みや相談を聞いて子育てのアドバイスをしたり、手助けしたりして里親をサポートする仕組みが今よりもっと充実したらいいなと思います。
私は里母のアドバイスもあり、専門学校を経て看護師になりました。家を出てシェアハウスに入ったのですが、社会的養護の子でも入れるシェアハウスを里母が探して、手続きもしてくれました。看護師になり、結婚して出産し、いまは育休を取って4カ月の男の子を育てています。自分が親になって思うことは、世の中のお母さんはすごい!ということです。本当に尊敬します。血のつながった子を育てるのも大変なのに、里親になって子育てするのはどれだけ大変だろうと思います。こどもも試し行動をしてしまうだろうし。それでも、どれだけ反抗されても、「私はあなたのことを大切に思っている」ということを、こどもには伝えてほしいです。
私自身は、自分の経験を生かして社会的養護の子の居場所づくりをしたり、こどもたちに「こどもの権利」について知ってもらう活動をしたりしたいなと考えています。
実はいま、里親とはささいなことでケンカして以来、数年連絡を取っていません。でも向こうは私に会いたいと思っていると思います。いつかのタイミングで、また会えたらなと思っています。

里母との出会いは一生の宝物
―多母髪大気さん(23)
僕は生まれて間もなく乳児院に保護されました。両親が薬物依存症で父は服役しており、母も養育能力がないと判断されたことが理由です。当時乳児院でお世話になった職員さんが、僕の里母になってくれました。
僕には生まれつき脳性まひがあり、生活するのに介助が必要です。いまも車いすで生活しています。当時、乳児院から障害児入所施設に移ることになったときに僕のことをとても気にかけて付き添ってくれたのが、里母です。
僕にとって里母との出会いは一生の宝物です。
障害児入所施設にいる多くのこどもには、両親がいます。普段は施設で暮らしていても、両親が面会に来てくれるし、週末は自宅に外泊できる。両親と暮らすことのできない僕ですが、里母が面会に来てくれたり、家に外泊させてくれたりしたので、孤独を感じずにいられました。いわゆる「週末里親」のかたちで、僕を支えてくれました。
両親が不在で、家族として機能しないという環境にある僕にとって、普通の家庭で過ごして温かいごはんを里母と一緒に食べるという経験は、何事にも代えがたい思い出です。

里母の後押しでスポーツにも果敢に挑戦
里母は成人したお子さんがいて少し年配なので、僕のことを孫のように可愛がってくれました。恥ずかしくて面と向かっては言えないのですが、優しい人で、僕のことを本当に理解してくれる人です。
僕は幼いころからスポーツが好きで、パラ卓球やパラ陸上を続けてきました。里母は道具を一緒に買いに行ってくれたり、パラスポーツの大会に連れて行ってくれたり、僕を後押ししてくれました。
思春期での反抗などは特になかったのですが、だんだんと僕が成長して体が大きくなっていく一方、里母は年を取っていくなかで、里母宅への外泊時に里母がうまく介助ができず、もどかしさから衝突することもありました。外泊はなかなか難しくなったけれども、その分卓球の試合に一緒に行こう、など、お互い気持ちを切り替えて、乗り越えました。里母が環境を整えてくれたおかげでスポーツに打ち込め、パラスポーツの指導員の資格も取れました。
いまはグループホームで暮らしているのですが、そこに入所するときも里母が保証人になってくれました。近所に住んでいるので、何かあると自転車で駆けつけてくれるので心強いです。
この春、僕は一般社団法人を立ち上げました。社会的養護への理解を深めたり、自分が歩んできた道のりを知ってもらう活動をしたりしたいと考えています。
社会的養護のもとにあるこどもの多くは被虐待児で、なかには障害がある子も多いです。社会的養護は児童福祉の分野ですが、障害児は障害福祉の分野です。社会的養護を受けているこどもが児童福祉から障害福祉に円滑に移行できるようにするなど、僕は自分の立場だからこそ発信できることを発信し、解決につなげるような活動をしていきたいです。障害があっても、家庭環境が複雑でも、自らの人生を自らで歩んでいける、そんな社会になればいいなと思っています。

里親家庭を増やして選択肢を多くしてほしい
―ゆうなさん(25)
私が里親家庭に迎え入れられたのは高校2年生のときです。一緒に暮らしていた母の交際相手から性的虐待を受けていたことが、保護の理由です。学校から、制服のまま保護されました。
交際相手と離れて母が暮らすようになれば親元に戻れるはずだったのですが、母は結局交際相手が購入した家に住んだままだったので、戻ることができなくなりました。
自分としては一時保護所から自宅に戻れると思っていたのに突然里親家庭に行くことになったことがショックで……。「一回お試しで里親家庭に外泊させてもらいたい」と頼み、聞き入れてもらいました。
訪ねたご家庭の方たちはとても優しそうで、ショッピングモールに連れて行って私の好きな雑誌を買ってくれました。フードコートで食事をして、私が「ごちそうさまでした」と言ったら、「家族になるのだからそんなふうに言わなくていいよ」と言ってくれて、すごくうれしくて一時保護所の職員さんに報告したことをよく覚えています。数日後から、そのご家庭でお世話になることになりました。
家族構成は里母さん、里父さんと、特別養子縁組で娘になった年下の女の子でした。衝撃的だったのは、女の子が親に怒られても、その数分後には普通に親子で会話していることです。私の実家では一度でも怒られたら、その日一日口をきいてはいけないような感じでした。食事が食べられない日もありました。
家を飛び出し、実家に戻ってしまったけれど
里親さんの家庭ではもちろん楽しかったこともあったのですが、結局、5カ月で私が家を飛び出して実家に帰ってしまい、里親家庭での生活は終わりました。
当時の私は不登校気味で、欠席したり遅刻したりを繰り返していたのですが、里親さんは「どうして」と聞いてくるのです。どうして行かないのだろうと心配してのことだと思うのですが、当時の私は怒られているような気持ちになってしまって。ちゃんと向き合って体調が悪いことを伝えたり、「実はこう思っている」と言ったりすればよかったのですが、私のほうが心を閉ざしてしまっていました。高2のころ、アトピー性皮膚炎がひどくて人前に出たくなかったのですが、それも言えなかった。もともと他人のおうちで「ちゃんとしなきゃ」と思う気持ちも強く、疲れてしまったというのもありました。里親さんが嫌だというよりは、誰とも関わり合いたくない、与えられた自分の部屋に引きこもっていたい気持ちでした。

母が交際相手と別居していたのでそのまま実家にとどまって通信制高校を卒業し、いまはひとり暮らしをしています。保護される前は母の言うことは絶対でしたが、里親さんとの生活を経て、母に言い返せるようになりました。また、IFCAでの交流やプログラムを通して、他人との線の引き方、たとえば自分の過去を全て話す必要はないこと、相手によってどこまで話すかを自分で決めていいことなどを学びました。
里親家庭を飛び出してしまった私ですが、里親は増えてほしいと考えています。里親が増えれば、里親家庭とこどものマッチングの選択肢も多くなります。ただ増やせばいいのではなく、社会的養護のこどもとの接し方など、知識も持つようになってほしいです。迎え入れられる子の多くは、言語化できない不安や困りごとを抱えています。私の里親さんも、決して悪気があったわけではなく、ただどう接していいかわからなかったのだと思います。里母さんも、時折相談先がないという愚痴を私に話していました。
IFCAに入って多くの里親家庭出身の子たちと話して、里親のかたちにもいろいろなものがあることがわかったことも、私が里親を肯定的に見る理由のひとつだと思います。
いま、里親になりたいと考えてくれている方たちは「自分たちにできるかな」とか、「本当にこどもを迎え入れられるかな」という不安が大きいと思いますし、真面目に考えてくれている方が多いと思います。里親さんに限らず、子育てに正解は絶対にないと思いますし、家庭だけ、両親だけとか、お母さんだけで子育てをしないといけないってこともないと思います。
児童相談所だったり他の第三者だったり、もっと色んな人と皆で子育するっていう感覚を持ってもらいたいなと思っています。自分たちの家だけで解決しないといけないということはないし、もっと色んな人を頼ってもらっていい。
そう思うと、里親になるハードルはそんなに高いわけじゃないよと伝えたいですね。